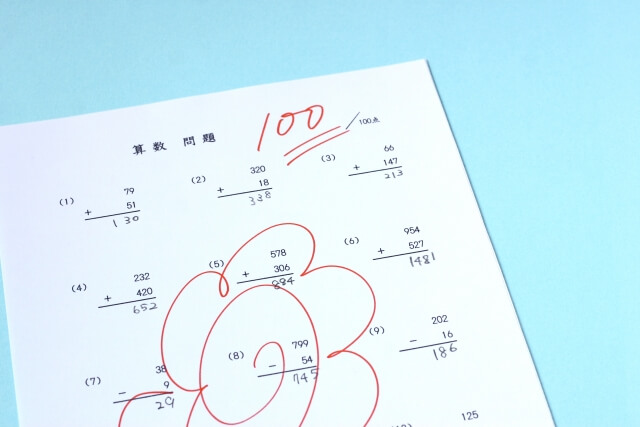秋になると、何故か寂しい理由
「秋になると、なんとなく寂しい」「夕方になると心が落ち着かない」「昔のことを思い出して涙が出る」
――そんな経験はありませんか?
実はこれは、多くの人に共通する“心の季節反応”です。
精神医学では、季節によって気分が変化する現象を季節性情動変化(Seasonal Affective Change)と呼びます。
中でも秋は、気温や日照、社会リズム、そして脳内ホルモンの変化が重なり、寂しさや感傷が生まれやすい季節なのです。
本記事では、精神医学的な知見をもとに、「秋になると寂しくなる理由」をわかりやすく解説します。
日照時間の減少が脳に影響する
秋のはじまりとともに、日照時間は一気に短くなります。
この「光の減少」が、脳の働きに大きな影響を与えることがわかっています。
脳内のセロトニンという物質は、太陽の光を浴びることで活性化します。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分の安定・集中力・意欲の維持に関わります。
しかし秋になると、日照量が減るため、セロトニンが減少しやすくなり、結果として「なんとなく落ち込む」「やる気が出ない」「孤独を感じる」といった状態になりやすいのです。
一方で、夜が長くなることでメラトニンという“眠りのホルモン”の分泌が増えます。
本来は睡眠を助ける大切なホルモンですが、日中も過剰に分泌されると、眠気や倦怠感を感じやすくなります。
つまり、秋の「眠い・疲れやすい・気分が沈む」は、脳が季節の変化にまだ順応しきれていないサインでもあるのです。
秋の「静けさ」は、心を内側に向ける
夏の喧騒が終わり、空気が澄み、虫の声が響く秋。
この「静けさ」自体が、脳にある変化を起こします。
何もしていないときに働く脳内ネットワークをデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)といいます。
このDMNは「自分を振り返る」「過去を思い出す」といった内省的な思考に関係しています。
秋は刺激が少なく、外的な情報が減ることで、このDMNが活発になります。
その結果、自分の内面と向き合う時間が自然と増え、過去の出来事や人間関係、失ったものなどが思い起こされやすくなるのです。
つまり、秋の寂しさは「感情の反芻」ではなく、脳が心の整理をしている自然なプロセス。
内省的な感情が強まる季節ともいえます。
社会的リズムの変化がもたらす「取り残され感」
秋は、社会的にも“中間地点”の季節です。
年度の折り返しを迎え、仕事や学校でも成果や進捗が見え始める時期。
夏のイベントシーズンが終わり、周囲の人間関係も落ち着いてくる。
このタイミングで、無意識に「自分はこのままでいいのか」「あの頃と比べて変わっていない」と感じる人が増えます。
社会的制約(仕事、学校、家事など)がある平日の睡眠と、生物時計と一致した制約のない休日の睡眠との差によって引き起こされる、“平日と休日の就寝・起床リズムのズレ”を、学術的にはソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)と言いますが、
この「取り残され感」は、ソーシャル・ジェットラグとも関連します。
身体は季節のリズムに合わせて変化しているのに、社会のスピードは止まらない――そのズレが「焦り」や「孤独感」を生むのです。
SNSを見て「みんな充実しているのに、自分だけ取り残されたような気がする」と感じるのも、秋に多い特徴。
実際は、誰もが同じようにリズムの変化に戸惑っている季節なのです。
「匂い」や「音」が呼び起こす感情記憶
秋の香りには、特別な力があります。
金木犀の香り、落ち葉の匂い、風に混じる少し冷たい空気。
これらはすべて、脳の扁桃体や海馬という“感情と記憶をつかさどる部位”を刺激します。
香りや音によって過去の情景がよみがえる現象を、心理学では「プルースト効果」と呼びます。
秋の匂いや虫の音は、過去の記憶と強く結びついており、懐かしさや切なさを呼び覚まします。
この“懐かしさ”という感情は、実は「快」と「哀しみ」が同時に存在する複雑な感情。
神経科学的には、報酬系と嫌悪系が同時に活性化している状態です。
だからこそ秋の寂しさは、「つらいけれど、どこか心地いい」という独特の味わいを持つのです。
現代社会で増えている「秋うつ(季節性うつ)」
近年、秋から冬にかけて気分が落ち込む「季節性うつ(Seasonal Affective Disorder:SAD)」が注目されています。
特にリモートワークなどで外出機会が減った人は、日光を浴びる時間が短く、セロトニン不足になりやすいといわれています。
主な症状は以下のようなものです。
朝起きるのがつらい
甘いものや炭水化物を過食してしまう
気力が出ず、何事も面倒に感じる
人との関わりを避けたくなる
体が重く、眠気が取れない
これらは単なる「秋バテ」ではなく、脳内の神経伝達物質バランスの乱れが関係しています。
治療法としては、光療法(ライトセラピー)や認知行動療法(CBT)、軽い運動などが効果的です。
また、朝に日光を浴びるだけでも、セロトニン分泌が促され、気分が安定しやすくなります。
なお、光は明るい蛍光灯でも効果的なので、寒くて出歩きたくない方もトライしてみてください。
寂しさは「心のリセットサイン」
精神科の立場から見ると、「寂しい」と感じること自体は悪いことではありません。
むしろ、心がしっかりと機能している証拠でもあります。
たとえば、強いストレスを受けているとき、人は感情を感じにくくなります(感情の鈍麻)。
しかし、秋のように静かな時間の中で寂しさを感じるのは、感情が再び動き出しているサイン。
つまり、心が“再起動”している状態なのです。
この時期に無理にポジティブになろうとせず、
「少し立ち止まって、自分の心を眺める」時間をもつことが大切です。
お気に入りの音楽や香り、お茶など、五感を満たす方法も効果的です。
感情を味わいながら、自分をやさしく再構築する――それが、秋を上手に過ごすコツです。
秋の寂しさに対する対処法
秋の寂しさを和らげる5つの習慣
-
朝の光を浴びる
カーテンを開けて5分でも日光を浴びると、セロトニンが活性化します。 -
リズムを保つ
就寝・起床・食事の時間を一定に保つことで、自律神経が安定します。 -
温かい飲み物をゆっくり飲む
ハーブティーやお茶の香りは副交感神経を整え、心を落ち着けます。 -
季節を感じる活動をする
紅葉を見に行く、秋の食材を楽しむなど、「今ここ」を感じることが心のリセットになります。 -
人と小さくつながる
短いメッセージや会話でも、社会的なつながりが孤独感をやわらげます。
おわりに:秋は「心を調律する季節」
秋の寂しさは、あなたが「感じる力」を持っている証拠です。
それは心が静かに回復し、次の季節に向けて整っていく自然な流れ。
気持ちが沈む日があっても、それを否定する必要はありません。
むしろ、「季節と一緒に心が動いている」と受け止めることで、
秋という時間は、より豊かで、やさしいものになります。
【引用・参考文献】
・Lam, R. W., Levitan, R. D., Morehouse, R., Michalak, E. E., Tam, E. M., Enns, M. W., … & Tam, E. M. (1999). Morning vs evening light treatment of patients with winter seasonal affective disorder. JAMA Psychiatry, 56(1), 79–87.
・McMahon, F., Todd, D., Craig, J., & others. (2014). Increased seasonal variation in serotonin transporter binding in seasonal affective disorder. Brain, 139(5), 1605–1614.
・Partonen, T., & Lönnqvist, J. (1998). Seasonal affective disorder. The Lancet, 352(9137), 1369–1374.
・Rosenthal, N. E., Wehr, T. A., Sack, D. A., et al. (1984). Seasonal affective disorder: A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy. Archives of General Psychiatry, 41(1), 72–80. [Note: original study; referenced via summaries]
・Sheline, Y. I., Price, J. L., Yan, Z., & Mintun, M. A. (2009). The default mode network and self-referential processes in depression. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(6), 1942–1947. PNAS
・ambuco, N., et al. (2023). Cognition, emotion, and the default mode network: A mini-review.
・Souter, N. E., et al. (2024). Default mode network shows distinct emotional and cognitive subsystems: An fMRI study.
・NHS. (n.d.). Seasonal affective disorder (SAD) – overview.
・National Institute of Mental Health (NIMH). (n.d.). Seasonal affective disorder.
・Sinyor, J., et al. (2023). Seasonality of brain function: Role in psychiatric disorders. Translational Psychiatry,
.png)