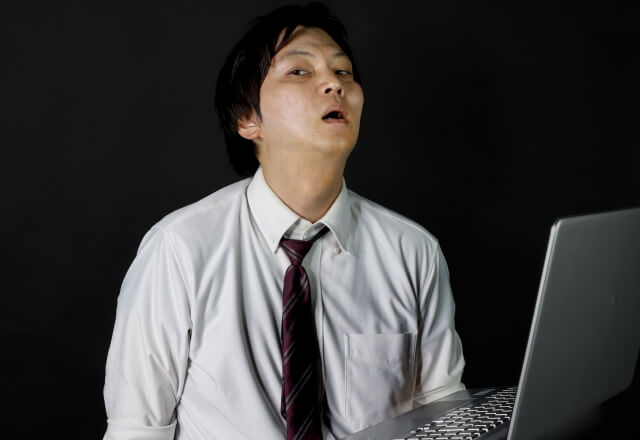
気分変調症とは
Summary
overview
気分変調症は2年以上続く軽度の抑うつで、生活は維持できるが心理的負担が大きく、早期治療が重要です。
cause
原因は遺伝・脳内物質・環境・性格、ストレスが絡む多因子とされます。生育歴や発症状況、併存要因まで立体的に総合評価が必要です。
diagnosis
気分変調症は2年以上抑うつ気分が続き、睡眠障害や疲労感などを伴います。診断には他の身体疾患や物質使用を除外することが必要です。
treatment
気分変調症の治療は抗うつ薬や心理療法を中心に、生活習慣の改善や社会的支援を組み合わせます。適切な治療で改善が可能です。
概要
気分変調症(Dysthymia)とは、長期間にわたる軽度から中等度の抑うつ状態を特徴とする慢性的な気分障害です。正式名称は「持続性抑うつ障害」とも呼ばれ、少なくとも2年以上続く持続的な抑うつ気分が主な症状です。この病気は全人口の約3-6%が一生のうちに経験するとされ、女性にやや多くみられる傾向があります。
気分変調症は、通常の生活は維持できるものの、日常的な喜びを感じにくくなり、社会的、職業的な機能が低下することがあります。発症のピークは青年期から中年期にかけてで、未治療の場合、うつ病のエピソードや他の精神疾患を併発するリスクが高まります。そのため、早期発見と治療が重要です。抑うつエピソードが見られるうつ病とは異なり、気分変調症は比較的軽度であるものの、その慢性的な性質によって患者の心理的負担が大きくなります。この病気は適切な診断と治療を受けることで改善が可能です。
原因
気分変調症の原因は一つではなく、以下のような複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。
1)遺伝的要因
気分障害の家族歴がある場合、発症リスクが高くなる傾向があります。遺伝的な要因が感情調節に影響を与えているとされています。
2)脳の神経伝達物質の不均衡
セロトニンやノルアドレナリンなど、感情や気分の調節に関与する脳内の化学物質のバランスが崩れることが一因とされています。
3)環境要因
長期的なストレスやトラウマ、社会的孤立、家庭や職場での問題などが引き金となることがあります。
4)性格傾向
完璧主義や過度に自責的な性格傾向を持つ人は、気分変調症を発症しやすいとされています。
上記のような多様な理由により、診断を得るだけでは治療の足掛かりは得にくく、病前性格や発病状況、受診理由や症状回復を妨げている因子、身体疾患やアルコールなどの物質が関与しないかなど、立体的な解釈が必要となります。
診断
気分変調症の診断は、精神科医や心療内科医による詳細な問診と診断基準に基づいて行われ、少なくとも2年間ほとんどの日で憂鬱な気分が続いている事に加え、抑うつの間は下記の2つ以上の項目が存在しなくてはなりません。
①食欲の減退または過食
②睡眠の障害(不眠または過眠)
③エネルギーの低下または疲労感
④自尊心の低下
⑤集中力の欠如または意思決定の困難
⑥絶望感
なお、2年の期間中で2ヶ月以上、症状がない時期がないことが診断の条件になります。これまではうつ病の診断閾値以下の、2年以上の慢性的な病態を指すものとされていましたが、うつ病の診断閾値に達する時期があっても診断できるようになりました。
また、他の精神疾患や物質使用、身体疾患によるものではない事も診断の上で必須となり、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症(特にビタミンB12)、慢性疲労症候群などの他の身体疾患や、アルコールや薬物の使用による物質関連障害の症状としての抑うつで説明が出来ないか鑑別も必要です。
治療
気分変調症の治療には、薬物療法と心理療法を中心に、生活習慣の改善や社会的サポートを組み合わせることが重要です。薬物療法では、SSRIやSNRIといった抗うつ薬が一般的に用いられ、場合によっては気分安定薬が併用されることもあります。また、不安焦燥やイライラに対してはエビリファイやルーラン、リスパダールといった抗精神病薬が使用されることもあります。さらに、認知行動療法(CBT)や対人関係療法(IPT)といった心理療法は、否定的な思考パターンや対人関係の問題を改善する助けになります。さらに、規則正しい運動や睡眠、バランスの取れた食事といった生活習慣の見直しも、治療の効果を高める要素です。気分変調症は長期間にわたる慢性的な障害ですが、適切な治療と支援を受けることで改善が可能です。
.png)






