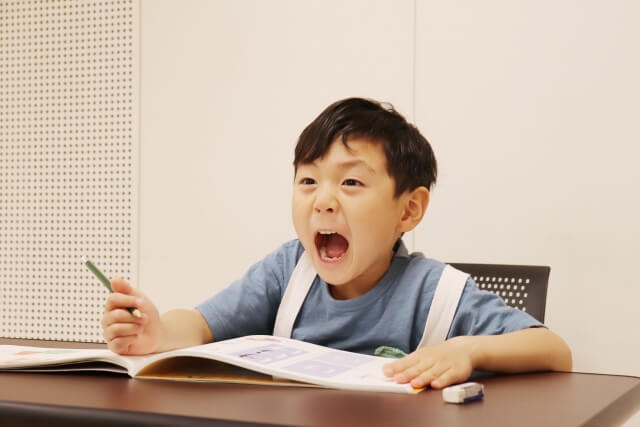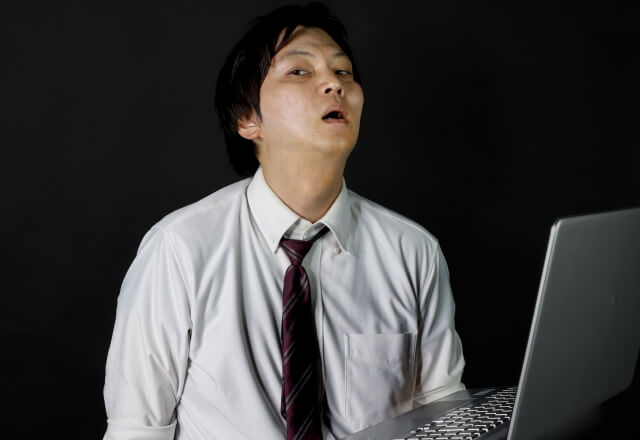解離性障害とは
Summary
overview
解離性障害はトラウマやストレスを背景に、感覚・運動や記憶・自我に異常が生じる病態です。
cause
解離性障害は幼少期のトラウマやネグレクト経験が背景にあり、不安や脳機能異常により発症します。
diagnosis
解離性障害は身体疾患や他疾患で説明できず、ストレスと関連し社会生活に支障を来す場合に診断されます。
treatment
解離性障害の治療は安全性の確立、外傷記憶の消化、再結合とリハビリを軸に進めます。
概要
解離性障害(DD:Dissociative Disorders)とは、運動機能や感覚機能、自我機能の異常が出現する病態のうち、身体医学的に説明できないものを言います。例えば、麻痺や脱力、めまい、失声、尿の出にくさ、触覚、痛覚などの消失や、視界の異常などが症状としてあげられます。健忘(解離性健忘)やいわゆる二重人格(解離性同一症)、現実感の喪失(離人症)が出現し、気が付けば別の場所にいて、名前や知人、職業を思い出せなくなる人もいます(解離性遁走)。ただし、詐病のようにわざとそのように振る舞っているのではなく、本当にそのような症状を呈しており、支障をきたしているものを言います(ただし、本人は他人事のように平然としている事があります)。疾患の背景には、心理的葛藤に悩んでいるか、ストレス耐性が低い、あるいはトラウマやアタッチメント喪失体験(いじめ、養育者の精神疾患、重病、虐待や事件)を経験している事が多いです。有病率は0.05%で、10代から20代にも多く見られますが、発症年齢の平均は30歳代であり、全体的には女性に多いとされています。症状の中では、女性はけいれん症状、男性は麻痺症状が多い事が知られています。操作的診断基準のうちDSMでは身体症状を呈するものを変換症、精神症状を呈するものを解離症と分けていますが併存も多く(30-50%)、共通病態と考えられます。うつ病やPTSD、不安障害などの合併は90%もあり、高頻度です。年齢が若く、病歴が短いと予後良好ですが、パーソナリティ障害があったり、疾病利得があったり、訴訟が絡むと予後不良であり、そうした例ではしばしば慢性化します。
原因
過去の体験が発症に関連しているとされています。小児期早期にトラウマ体験やいじめ、ネグレクト・重病、隔離体験などを経験すると、発症リスクを高めます。高度の不安感の結果から出現する症状と考えられており、ストレス耐性の低い人にも出現しやすいです。脳神経学的には、感覚連合野と角回型(感覚連合野の失調)、前頭ー辺縁系型(不安による皮質の扁桃体抑制による交感神経系と情動抑制の異常)による二つのモデルが考えられています。
診断
解離性障害の症状は、概要の項で述べてあるよう多彩であり、それぞれの症状に対して診断名が用意されています(解離性健忘、解離性遁走など)。ただし、いずれも症状が出現している際には現実検討能力が保たれており、かつ職業的あるいは社会的に、またはその他の重要な領域で障害があることが診断の条件になります。解離性障害と診断するには、以下の条件を全て満たす必要があります。
①障害を特徴づける症状を説明可能な身体的障害を証明できないこと
②症状発生と、ストレスの強い出来事や問題あるいは要求との間に、明らかに時期的な関連性を認めること
また身体や脳の病気による錯乱や妄想、てんかん、薬物中毒や他の精神疾患(統合失調症、うつ病、PTSD、パニック障害、急性ストレス障害、パーソナリティ障害など)がある場合、それらに伴って生じている可能性が十分考えられるため、その場合は解離性障害を主診断としないことが多いです。
治療
患者さんの不安や恐怖、状態像の全体を評価しいつつ治療を進めていきます。治療は①安全性の確立、②外傷記憶の想起とその消化、③再結合とリハビリテーションの3つの軸からなります。①安全性の確立は、診察場面を含めて患者さんを取り巻く環境を安全に整え、治療の準備を整える段階です。本人の訴えを優しく傾聴し、支持的に関わることでさらに本人が話しやすい環境を作り、診察場面を離れても虐待などがある環境から隔離し、保護することが治療の準備となります。もし、睡眠や食欲、気分などに著しく問題がある場合はそれぞれの状態に応じた薬物療法を試みられます。続いて、②外傷記憶の想起とその消化ですが、外傷記憶と向き合い、それにまつわる不安恐怖を和らげてこれを克服する段階です。過去の出来事の周辺領域を話題とし、未来の希望へつなげるよう支援します。その際、主としてCBTやEMDRなどの心理療法が用いられます。③再結合とリハビリテーションとは、日常生活における不安や恐怖を克服することです。日常の些細な出来事に関して不安や恐怖を感じないように、心理療法や理学療法を継続していきます。保護的な環境では改善も悪化もするので、本人の状態を見極めつつ適宜治療介入することが大切です。お薬をいたずらに増量するのは望ましくなく、あくまで対症療法的に薬剤を用いていきます。
.png)