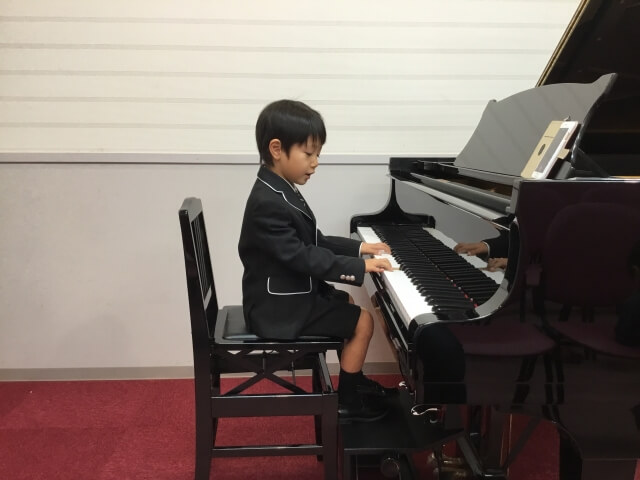
社交不安症とは
Summary
overview
社交不安症は、人前での評価や恥を恐れ強い不安を感じる病気です。多くは思春期に発症し、女性に多く併存疾患も多いです。未治療では長期に持続し生活や社会に深刻な影響を及ぼします。
cause
社交不安障害は扁桃体や前部帯状回など脳機能異常や遺伝が関与します。低い自己評価や否定的思考が罹患リスクを高め、交流回避と不安増悪の悪循環が進行要因となります。
diagnosis
社交不安症は6か月以上、人前で強い不安が続き生活に支障をきたす状態です。他疾患や身体疾患では説明できず、広場恐怖症との鑑別も重要です。
treatment
社交不安障害の治療はSSRIを中心とした薬物療法とCBTが基本です。薬は1年程度継続し、心理療法では呼吸法や行動実験で不安対処力を高めます。
概要
社交不安障害(SAD:Social anxiety disorder)とは、他人の注視を浴びるかもしれない状況に対して、著しく恐怖心が高まる病気です。自分が恥をかいたり、拒絶されたり、否定的に評価されることを恐れる病態とされています。社交不安症や社会恐怖症とも言われ、俗にはあがり症とも言われています。恐怖の対象は、人前での会話や書字、公共の場所での飲食、よく知らない人との面談などが挙げられています。症状としては、話をしているときに声が震えたり顔が引きつる、またその有様を「他者からに気づかれてしまうのでは」といった不安や、不安に伴う自律神経反応が現れやすく、紅潮、動悸、振戦、声の震えや発汗、胃腸の不快感や下痢などの症状を呈することがあります。病状が進行すると、社会的活動を回避する事が多くなり、日常生活に困難をきたすようになります。米国では、12ヶ月有病率は7%ほどと推定されており、欧州においては2%ほどとされています。日本では、12ヶ月有病率は0.7%、生涯有病率は1.4%と報告されており欧米と比較して有病率は低いとされていますが、自己主張の少ない態度が日本的であることもあって、正常の範囲とみなされてなかなか診断されないためであるとする向きもあります。75%は8〜15歳程度の早期発症です。女性に多く、5歳と11−15歳に発症のピークがあります。成人期における発症は比較的まれですが、ストレスの強い出来事や職場での昇進など新しい社会的段階を求められるようになるといった、生活環境の変化があった後に発症する事があります。治療しない場合、60%程度は数十年にわたり症状が持続します。また、社交不安障害の患者は、退学率が高く、職場での生産性や生活の質が低下し、未婚、離婚や子供をもたない可能性が高まるとされています。6割近くに併存疾患がみられ、不安症、うつ病、アルコール使用障害などの併存が多いとされていて、併存すると自殺念慮、自殺企図の危険が高まります。社交不安障害の症状を呈する患者が急激に爽快な気分を呈し活動量が増え、のちに双極性障害と診断変更される例もあります。
原因
病態生理としては、特定の脳領域の機能不全が指摘されています。専門的には、扁桃体、前部帯状回皮質、島皮質のセロトニン5-HT1A受容体結合能が低下し、線条体におけるドパミンD2受容体と、ドパミントランスポーター結合能が減少しているという報告などがあります。遺伝の関与が指摘されており、第一度親族が社交不安障害であれば、罹患する確率は2–6倍高くなるとされています。心理的には、低い自己評価と関連しており、自己にたいする否定的な考えが強い方が罹患しやすいです。社会的な交流を回避するようになり、自信がなくなることでさらに不安が強まるという悪循環が病態を進行させます。
診断
社交不安障害の診断は、以下の全てを満たし、かつ他の医学的疾患や精神疾患で説明できない事で診断されます。なお、症状は典型的には6ヶ月以上続くことが多いです。
①他者の注視を浴びる可能性のある複数の場面で、著しい恐怖または不安を感じる
②不安症状として表出される行動が、否定的な評価を受ける事になる事を恐れている
③社交的状況では、常に不安を誘発する
④その社交的状況は回避され、または強い恐怖または不安を感じながら耐え忍ばれる
⑤その恐怖または不安は、その社交的状況がもたらす危険や、その社会文化的背景に釣り合わない
⑥その恐怖、不安または回避は持続的で、典型的には6か月以上続く
⑦その恐怖、不安、または回避は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こす
⑧物質または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない
⑨パニック症、醜形恐怖症、自閉症スペクトラム症といった他の精神疾患の症状では、うまく説明されない
簡単に言うのであれば、目立つ場面や社交場面で著しく不安が高まり、結果として日常生活に支障をきたす状態が続いている方を言います。他の医学的疾患や精神疾患で説明できないものと考えておくとよさそうです。公共交通機関でしばしばパニック発作を起こすなど症状が類似しているため、広場恐怖症と鑑別が必要になる事が多いのですが、こちらは背景に「人に迷惑をかけたくない」という思考が強いため、同伴者がいると逆に症状が悪化する事が多いです。
治療
治療は薬物療法と心理療法が主となります。薬物療法では、SSRIを中心とする抗うつ薬が主体となります。治療効果は3ヶ月程度みて、可能であれば1年継続することが推奨されています。抗うつ薬の反応率は、6〜7割程度です。1年程度寛解が維持できていたら、薬剤を少しずつ減らし、最終的にはなくしてみます。心理療法では認知行動療法(CBT)が一般的で、リラクゼーションスキルの構築(呼吸法、マインドフルネス法など)、否定的な考えの変容などをテーマに扱っていきます。ある程度不安に対処できるようになったら、できるだけ回避行動をとらないで、その結果がどうなったか確認してもらう(行動実験)を行います。
.png)






