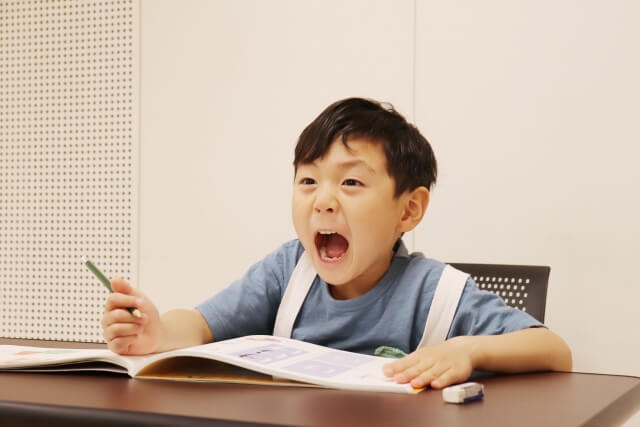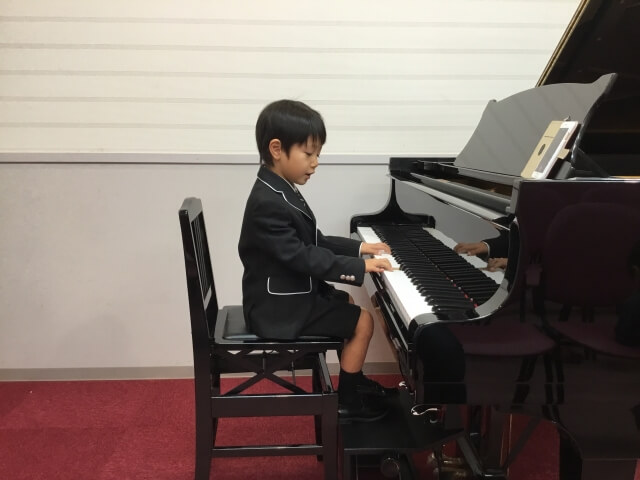不眠障害(非器質性不眠症)とは
Summary
overview
不眠障害は、入眠困難や早朝覚醒などで日中に支障をきたす睡眠障害で、日本人の約1割が罹患し、慢性化や心身疾患のリスクを伴います。
cause
不眠は心理・生理・行動・環境要因が複雑に関与し、ストレスや性格傾向、生活習慣、疾患や薬の影響などが相互に作用して生じるとされています。
diagnosis
不眠障害は3か月以上続く入眠・中途・早朝覚醒と日中機能障害が条件で、他疾患を除外し、睡眠日誌やPSGで評価されます。
treatment
不眠治療は行動習慣の改善とCBT-I(カウンセリング)が基本で、薬は補助的に使用します。心身の不調のサインとして早期受診が重要です。
概要
不眠障害は、適切な環境で眠ろうとしているにもかかわらず、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠感の欠如などの症状を呈し、日中の活動に支障をきたす睡眠障害の総称です。
現在の日本は高齢化、夜型化、ストレス社会、シフトワークの常態化などで、不眠障害のリスクはさらに高まっています。日本人の30%以上が不眠症を経験し、10%程度が不眠障害と診断されます。急性ないし一過性の不眠を経験した人の半数が、慢性的な不眠に至るという指摘もあります。高齢者では頻度が高く、男性よりも女性に多いとされています。
一般的に不眠症状は青年期に発症することが多いのですが、女性には更年期にも発症する可能性が高まります。
慢性的な不眠は、うつ病、不安障害、認知機能低下、高血圧や糖尿病などの身体疾患リスクを高めるとともに、長期欠勤や不登校の原因ともなり得るため、社会的機能の低下も懸念されます。ストレス性の出来事の後、あるいは環境変化に伴う急性不眠は、通常であれば数日から数週間持続し、状況が改善すれば消失しますが、心理的な脆弱性をもつ例では状況が改善したあとも不眠が持続したり、軽微な出来事で再発することもあります。現在では依存性のない薬剤が主体となっているにもかかわらず、睡眠薬を開始した人の30%が、6ヶ月超の長期にわたって睡眠薬を服用すると言われています。
原因
不眠の原因は一つではなく、心理的、生理的、行動的、環境的な要因が複雑に絡み合って生じます。心理的要因としては、仕事や人間関係のストレス、不安、抑うつなどが代表的であり、特に「眠れないこと自体」への恐怖や焦りが悪循環を形成していくケースも多くみられます。こうした睡眠関連不安が強まると、眠れない夜が続くたびに「また眠れないのでは」という予期不安が生じ、交感神経の緊張が高まることで、さらに入眠が妨げられるという自己強化的なパターンに陥ります。元来、神経質だったり几帳面な性格の人にこのパターンが多いです。
また、行動や環境に起因する要素も重要です。就寝直前までスマートフォンを操作したり、カフェインやアルコール、タバコを摂取したりする習慣は、脳を覚醒状態に保ってしまいます。夜間の強い照明やエアコンの過度な使用、昼夜逆転した生活リズムも睡眠の質を低下させます。さらに、眠れないままベッドに長時間横たわることが続くと、「寝床=眠れない場所」と脳が学習してしまい、寝室に入るだけで覚醒してしまうという行動学的な悪循環が形成されます。
生理的な側面では、加齢に伴うメラトニン分泌の低下や体内時計の変化、ホルモンバランスの乱れ、更年期、慢性的な痛みや夜間頻尿、呼吸器疾患、甲状腺機能異常などが不眠を引き起こすことがあります。とくに高齢者では、深睡眠の割合が減少し、夜間の中途覚醒が増える傾向があります。さらに、概日リズム睡眠障害の一種である「睡眠相後退症候群」など、体内時計のずれが背景にある場合もあります。
精神疾患や薬剤の影響も見逃せません。うつ病や不安障害、双極性障害、統合失調症などでは、不眠が初期症状または再発のサインとして現れることが多く、治療経過を見極める上で重要な手がかりとなります。また、ステロイドや抗うつ薬の一部、β遮断薬、覚醒作用を持つ薬剤などが睡眠に悪影響を及ぼすこともあります。これらの場合は、不眠障害として診断されず、該当する精神疾患や薬剤性不眠と診断されることになります。
子どもの頃から寝付きが悪い場合は、遺伝的体質が原因ではないかと考えられています。
診断
不眠障害の診断は、DSM-5やICD-10/11の診断基準に基づいて行われます。
A. 以下のいずれかの睡眠困難が、週に3夜以上みられ、3か月以上持続していること。
・入眠困難(寝つきに30分以上かかる)
・睡眠維持困難(夜間に複数回目が覚める)
・早朝覚醒(予定より2時間以上早く目が覚める)
B. 日中の顕著な機能障害を伴うこと
・倦怠感、集中力・注意力の低下、気分の落ち込み、焦燥感、日中の眠気、多動、無気力、夜間睡眠のこだわりなど。
C. 他の睡眠障害、身体疾患、精神疾患、または薬物の影響によるものではないこと。
診断には、睡眠に関する自覚症状だけでなく、その影響が日中の機能に及んでいるかどうかが重視されます。また、診断の過程では、睡眠日誌やアクチグラフによるリズム評価、必要に応じて終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)などを行い、他の睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、レム睡眠行動障害など)との鑑別を行います。
治療
治療は原因に応じて多面的に行われますが、まず第一に重視されるのは薬に頼らないアプローチです。睡眠衛生の改善と認知行動療法(CBT-I)は、長期的な再発予防にも効果が高いとされています。具体的には、就寝・起床時刻を一定に保つ、就寝前の電子機器使用やカフェイン摂取を避ける、日中に適度な運動と自然光への曝露を取り入れる、就寝前のリラックス法を身につける、そして「眠れない時には一度ベッドを離れて静かに過ごす」などの行動修正を行います(参考)。認知行動療法では、「8時間眠らなければいけない」「眠れなかったら明日がダメになる」といった極端な信念を修正し、睡眠に対する過度なプレッシャーを軽減します。
薬物療法は補助的に用いられます。短期的には非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(ゾルピデム、エスゾピクロンなど)が有効ですが、耐性や依存のリスクを考慮し、最小限の期間に留めることが原則です。近年では依存性が少ないメラトニン受容体作動薬(ラメルテオン)や、オレキシン受容体拮抗薬(デエビゴ、ベルソムラ、クービビックなど)が主流となっています。これらは自然な睡眠リズムを整える効果があり、高齢者にも比較的安全に使用できます。併存するうつ病や不安障害がある場合には、抗うつ薬や抗不安薬を併用することもあります。
不眠障害は単なる睡眠の問題ではなく、心身の健康を映し出す「バロメーター」としての側面を持ちます。適切な治療を受けることで、睡眠の質だけでなく、気分、集中力、体調、そして生活全体の満足度が改善することが期待できます。眠れない夜が続くとき、それは単なる「寝不足」ではなく、心身のサインである可能性があります。早めに専門医に相談し、自分に合った治療法を見つけることが大切です。
.png)