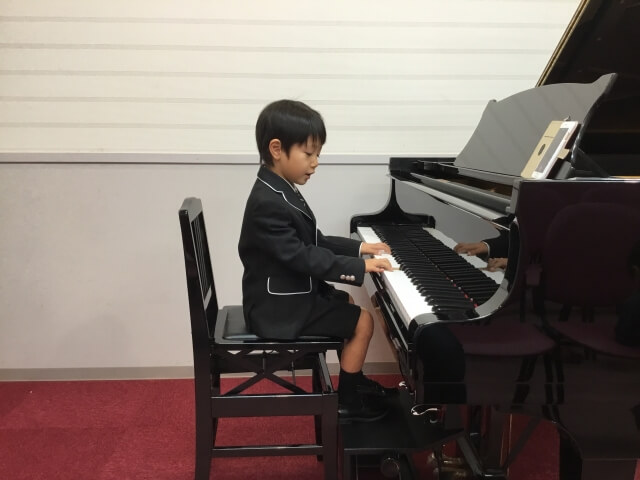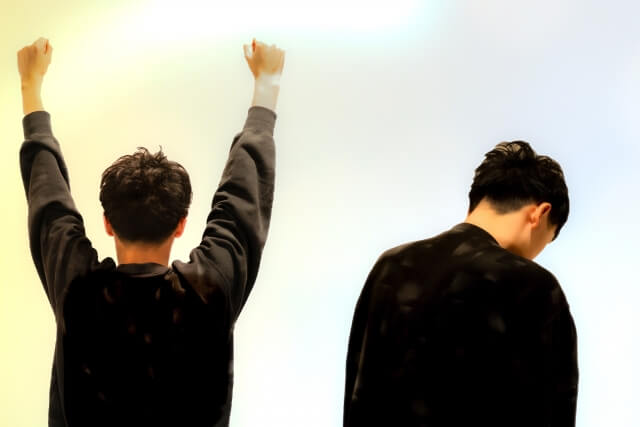うつ病(MDD)とは
Summary
overview
うつ病は抑うつ気分や興味喪失を特徴とし、女性に多い。再発率が高く「脳の骨折」とも呼ばれます。
cause
うつ病の原因は未解明ですが、遺伝や脳機能異常、神経伝達の低下など多因子が関与すると考えられます。
diagnosis
うつ病は抑うつ気分や興味喪失などが2週間以上続く場合に診断され、問診が中心で鑑別が重要です。
treatment
うつ病治療は生活改善が基本で、中等症以上は抗うつ薬を使用し、必要に応じ認知行動療法やECTも行います。
概要
うつ病(大うつ病性障害:MDD major depressive disorder)とは、抑うつ気分や興味関心の低下などの症状を主体とする症候群です。通常、中年から初老期にかけて好発します。うつ病の症状は大なり小なり持続し、全く不調感がない日があれば通常診断されません。睡眠障害や食欲変化など、何らかの身体症状がほとんどの例で出現します。また、不安や自責、絶望感なども出現する事があります。朝、特に不調を自覚するなどの日内変動や、集中力の低下も特徴的な所見です。日本においては、うつ病の生涯有病率は6.16%(男性3.84%、女性8.44%)程度とされており、女性に多い疾患とされます。かつては高い有病率から「脳の風邪」と言われていましたが、適切に治療しなければ集中力の低下が残ったり、肥満のリスクが上がったりする等、後遺症が残る場合もあり、再発率も60%以上であることから、「脳の骨折」と呼ぶ方がふさわしい疾患であると言えます。
原因
原因については、まだ明確にわかっていません。極めて特異的な所見というのは未だなく、一つの原因というよりは、遺伝、病前性格、感染症、脳機能の異常など多彩な病態が関与していると思われています。脳機能異常に関しては、扁桃体/眼窩前頭皮質の活動亢進、脳梁膝下部前頭前野の活動低下や、炎症性神経障害、視床下部–下垂体–副腎皮質系の機能異常、セロトニン、ノルアドレナリン神経伝達の低下などが推定されています。特にセロトニン、ノルアドレナリンの神経伝達の低下が原因ではないかとする考え方はモノアミン仮説と呼ばれ、抗うつ薬の治療効果の理論的根拠となっています。
診断
以下の臨床症状のうち、5つ以上の症状が2週間以上持続しているとき、それらの症状により社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている場合に診断されます。ただし、症状の少なくとも1つは①ないし②であること、症状が身体疾患や物質による影響で説明できないことが診断の条件となります。
①その人自身の言葉か、他者の観察によって示される一日中、毎日の抑うつ気分
②ほとんど一日中、毎日のほとんどすべての活動における興味または喜びの著しい減退
③ひと月で5%以上の体重変化、またはほとんど毎日の食欲減退または食欲増加
④ほとんど毎日の不眠または過眠
⑤ほとんど毎日の落ち着きのなさ、あるいは動きの緩慢さ(主観的な感覚ではなく、客観的に観察されるもの)
⑥ほとんど毎日の疲労感、または気力の減退
⑦ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感
⑧ほとんど毎日の思考力や集中力の減退、または決断困難
⑨死についての反復思考、自殺念慮または自殺企図、自殺するための計画
実際には患者さんの表情や動き、思考の鈍さや表出ぶりなどを主治医の経験や感性で処理し、最終的な診断を検討する事もあります。診断がどの医師も同じになるよう、精神科医はトレーニングを受けていますが、人間である以上捉え方に差が生まれたり、患者さんが語る内容も刻々と変化するために診断は変化する可能性があります。現に、うつ病と診断された患者さんのうち10%以上が双極性障害に診断変更されているようです。
2014年に光トポグラフィー(NIRS)が抑うつ症状を呈する鑑別診断の補助として保険適用されましたが、診断基準が問診で得られる所見を基準に設定されているため、どうしても問診の方が診断の為には優れている、というのが現状です。今後、うつ病の原因の理解が深まり、生理学的所見や脳画像などで疾患が捉えられるようになれば、客観的な検査でうつ病を診断できる時代が来るかもしれません。うつ病と鑑別が必要な疾患として、適応障害、双極性障害、脳腫瘍などの器質性脳疾患、認知症、統合失調症などがあります。
治療
食事や睡眠状態の改善、ストレスや飲酒、喫煙の回避などの生活週間の改善をベースとして、中等症以上であれば抗うつ薬と主体とした薬物療法を検討することが多いです。抗うつ薬は、かつては三還系抗うつ薬と言われる、良く効く代わりに副作用の頻度が高い薬剤が使用されていましたが、近年ではSSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬、S–RIM(セロトニン再取り込み/セロトニン受容体モジュレーター)と言われる副作用が比較的少ないタイプが第一選択として好まれる事が多いです。最初は症状に合わせて1から2週間に1度のペースで来院してもらい、少量の薬剤から開始、副作用と効果をみながら増量していきます。いずれの薬剤も効果を判定するには最低3〜4週間程度必要となることには注意が必要です。無効ないし効果不十分であれば、抗うつ薬を変更したり、増量ないし別の薬を少量追加したりします。副作用が強く出現した場合は、無理せず中止することが推奨されます。抗うつ薬の反応性は初回治療でも60%程度のため、無効の場合もしばしばあるため、5種類程度は抗うつ薬を試みられます。抗うつ薬に対する偏見から、症状が改善したらすぐに辞めてしまう患者さんも多いですが、再発予防のため、一般的には抗うつ薬は4〜9ヶ月程度の服薬の継続が推奨されます。幻覚や妄想が出現していたり、食事が取れなかったり、希死念慮が強く生命の危機が迫る重症の場合は、入院の上で電気けいれん療法(ECT)が優先される場合があります。軽症うつ病の場合は、薬物療法のメリットよりも、悪心・嘔吐や頭痛、無感情、被刺激性亢進、不整脈、中止後症候群のリスクなどの副作用のデメリットが上回る可能性があるため、医師とよく相談して薬物療法の導入を検討されます。再発が多い症例では、ストレスへの対処法を身につけるため認知行動療法が推奨されます。
.png)